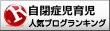こんにちは、ゆうです。
目次
- お子さんが発達障害と診断されてから、あなたはどんな想いを抱えてきましたか?
- なぜ旦那さんは障害を理解してくれないのでしょうか?
- 発達障害で受診している病院へ、一緒にいきましょう。
- 旦那さんと療育へ見学にいく!
- 今後、お子さんの診断名がついているのに、旦那さんが理解しない。困るのは誰でしょうか?
- まとめ
お子さんが発達障害と診断されてから、あなたはどんな想いを抱えてきましたか?
・(そんなはずない、違う病院に行ってみようかしら…)診断名を疑ったり…
・(やっぱり障害はその通りだった…)落ち込んでみたり、
・(親がしっかりしないと!)責任感を感じたり…
・ママ友さんと話して、少し前向きになれたり…
きっと診断されてから色々なことがありましたよね?診断されてから、一番辛い事って何でしたか?私の友人は、こう言いました。
『夫の理解が得られない事』

発達障害児を育てていく上で、家族の協力は必須です。そんな夫が自分の子どもの障害を受け止めきれず、目を逸らし続けている状況。
・『俺らが子どものころは、こんな感じの子どもいっぱいいたよ』
・『俺も昔こんな感じだった。障害なんて決めつけるなんて早いんじゃないの?』
・『育て方にも問題あるんじゃないの?』
こんな風に言われていませんか?大変な状況もわかってもらえず、協力もしてもらえない。とても辛いことですよね。
私も、なかなか家族の理解が得られない時があり苦労しました。現在では子供の障害を理解をしてくれ、協力してくれるようになりました。そんな私の試行錯誤の結果をご紹介したいと思います。
この記事を読んでいただければ、

・障害児に対する家族の理解が深まる。
・夫が育児に協力的になる。
・家族関係がうまくいくことで、子どもの笑顔が増える。
・ママ自身が前向きになれる。
などが考えられます。
ちなみに、現在の私は、夫に障害児2人を預けて1泊旅行ができるまでになりました!ここまで来るのはとても長かったですが…少しずつ…着実に夫の理解を深めようと努力してきました。
まず、あなたへ質問です。
なぜ旦那さんは障害を理解してくれないのでしょうか?
・プライドが高いから、障害を認めたくない?
・できれば健常児と同じように育ってほしいから、発達障害児と思いたくない?
色々あると思います。
私の考えは、『夫が障害だと理解できる回数(時間)、子どもの状況を見ていないから』だと思います。
4歳のお子さんとママが一緒にいる時間を計算しました。寝る時間を8時間とすると、233600時間。
今度は、お子さんとパパが一緒にいる時間を計算してみましょう。たとえば、平日パパの帰りが夜の7時とします。起きるのは朝7時で8時に出勤とします。ということは、寝るまでの2時間、朝は1時間の計3時間。休日は、ママと同じ時間にしたとして、9024時間。
(233600÷9024≒25)
パパと子どもが一緒にいる時間はママの1/25です!!
ということは…
あなたが子どものトラブルを1日3回見たとします。1日に3回癇癪起こしたり、トラブルを起こしたとしても、パパからするとその出来事は8日に1回しか目の当たりにしないという計算になります。

1週間に1回あるトラブルと、
1週間に21回トラブルを見ているのでは全然違いますよね?
ということは、夫が障害に対しての認識が薄いのも時間的に無理はないと私は思います。
逆を言えば、あと25倍の時間をパパと子どもが一緒に過ごし、トラブルをママの8倍目の当たりにすれば、確実に理解してもらえると思います。しかし、仕事もあるのでそれは不可能ですよね。
では、それを踏まえた上で、どうやって夫の理解を少しでも深めていくのかを解説します。
結論を言うと、『夫を病院と療育に連れていく』です。
百聞は一見にしかず。実際の子どもの様子を見てもらうのです。(*療育とは障害のある子どもがよりよい生活ができるように、また将来の自立や社会参加に向けて訓練をする場所です。)
発達障害で受診している病院へ、一緒にいきましょう。
『お前だけで行けるだろ?俺は仕事があるんだ。』って言われてしまうんです…。はい、そう思います。そんなパパだから、障害の理解がないんですもんね。
しかし、パパが病院へ行ってくれるようになる魔法の言葉があります。ぜひ使ってみてください。

『あのね…病院の先生…女だからかママだとなんだか見下して話す人なの。毎回行くのが怖いの。心細いの…。相手が男の人だと態度が変わるみたいなのよ。ためしにパパも一緒に来てくれないかなぁ…?』(泣きそうな顔で言ってみてください!あなたは今だけ女優です!(笑))
これを言うと、『あ、俺が守ってあげなきゃ』って思うのか…私の主人は平日お休みを取ってくれました!
旦那さんと療育へ見学にいく!
療育の先生に『主人の障害理解を深めるために、ここに連れてきたいです。何か良い方法ないですか?』と聞いてみてください。たとえば”契約者本人の署名が必要だ”など、なんでもいいんです。1回でもいいです。療育に連れていきましょう。療育での様子を実際に見てもらいましょう。
実際にトラブルやできないことを何度か目の当たりにしたご主人は何ていうと思いますか?『やっぱり…〇〇はできないことが多いんだね…。ちょっとショックだったよ。ママの大変さがわかったよ。』
こんな風に言ってきたら、心の中でガッツポーズ!!!!大成功です!少しずつ、育児に関してパパの役割を増やしていきましょう。きっと文句言わずにやってくれると思います。
最後に、質問です。
今後、お子さんの診断名がついているのに、旦那さんが理解しない。困るのは誰でしょうか?
あなたと私は同意見だと思います。答えは、『子ども』です。

子どもの障害から目を逸らし続けた結果、困るのは子どもです。もう一度いいます。あなたのお子さんが一番困ります。必要なサービスを受けることができず、路頭に迷う可能性があります。
お子さんが小さい今から少しずつでいいので、パパが子どもを見る時間を増やしていきましょう。あなたが仮病を使ってでも、パパと子どものいる時間を増やすのです。絶対に、気づいてくれるはずです。
まとめ
『夫が育児に協力的になるためには…』について話しました。
パパと子どもは一緒にいる時間が圧倒的に少ないため、パパの認識が薄いのは仕方がない。ママと同じ認識になるのは不可能。
その上で、障害理解を深めるためにできることは、病院と療育に連れていくこと。
という話をしました。
ママは、いつもいつもいつも…子どもを一番に思い、頑張っていますよね。本当にお疲れ様です。誰にも褒められることにない孤独な戦いです。でも、ここに味方はいます。少しずつでいいです。行動してみましょう。お互いに頑張りましょう!
今日もお付き合いありがとうございました。
子育て中に、アドラーの心理学と自己理解を一緒に学んでみませんか?
言語聴覚士という専門家だった私が、発達障害児・双子を育ててみて、わかったことは3つ。
1,自分という人間を知れば、子育てがしやすくなる
2,失敗敗を何度も許された人が、人の失敗を許せる
3,自分を律することができるのは、選択肢を持ち選んできた人
私が子育て中に、人が変わったと言われるのは、アドラーの心理学と自己理解があったからと自信を持って言えます。
ぜひ一緒に学んでみませんか??^^
↑クリック。
記事が参考になったと思ったら、押していただけると助かります。
Twitterでは、子育て中の気づきを毎日発信しています。
フォローいただけると嬉しいです。
ゆう@発達障がい児×双子ママ (@syuhutago25) on Twitter
ママは、いつでも100点満点!!今日も頑張りすぎずにいきましょう!