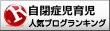今日は、 本田秀夫先生✕株式会社Kaien 鈴木慶太氏「発達障がいのある方の『地域で自分らしく働き生きていく』を考えるイベント」Youtubeの概要説明とここは、皆さんに知ってほしい!と思った所を厳選したいと思います。
本田先生のYoutubeは、なぜ有料でないのか…めちゃくちゃ価値ある動画なので、ぜひ皆さん、本田先生をご存じない方は、必見です。
目次
- 「発達障がいのある方の『地域で自分らしく働き生きていく』を考えるイベント」Youtube
- 理想は周りの大人が発達特性に早期に気づいてそれに沿った育て方をしていること
- 発達っ子の家族ができる唯一のこと、それは…
- 子どもの好きなことを否定しないであげましょう。
- 周囲は情報提供ができるようにしておけばOK
「発達障がいのある方の『地域で自分らしく働き生きていく』を考えるイベント」Youtube
理想は周りの大人が発達特性に早期に気づいてそれに沿った育て方をしていること
上記は、講義内の本田先生の言葉です。
大人になって初めて発達障害と診断された場合、発達特性と、その人がどんな背景を背負って育ってきたか…の両方を見なければならず、どんどん複雑化します。二次障害の精神疾患のほうが重篤化してしまった場合、もう遅い…となってしまうわけです。
発達っ子の家族ができる唯一のこと、それは…

親が子どもにこうなってほしい…こんなことができるようになってほしい…という理想を捨てること。
私はこう解釈しました。結局は、アドラーにたどり着いてしまうんだよなぁ。
『課題の分離ができているか?』
自分と子どもは、別の人格を持っていて、この子は大丈夫、生きていけると信じることができるか…。
就学前だと、身辺自立もイマイチだったりすると不安になるのは当たり前だと思います。しかし、徐々に身辺自立ができてくると『あ、大丈夫かもしれない』って思えるようになります。
絶対大丈夫なのです。
日本という国に生まれて本当にラッキーだし、行き倒れないシステムができてますから。
何より人間は、愛されて産まれてきているわけですから。
以前にも言いましたが、誰かに助けて…って言えることができればもう自立も近いってことです。安心して、子どもが『助けて』と言える環境を私達は作っていくべきではないでしょうか。
子どもの好きなことを否定しないであげましょう。

受け入れてあげなきゃ…私も好きになってあげなきゃ…ということではありません。
『そう、あなたはそれが好きなのね』と声をかけてあげましょう。
ゲーム三昧していても、それはその子の人生なのです。
親としては、『ゲームばかり…ダラダラして…将来どうなることやら…』と思うかもしれません。親は長期スパンの視点を持っていますが、子どもは『今』を生きています。それがどれだけ素晴らしいことか。
子どもでいられる時間って、18年しかないわけですよ…。それに比べて、大人って何十年ありますか?
子どもが子どもでいられる時間は有限です。
思いっきり遊ぶ権利を保証してあげましょう。
周囲は情報提供ができるようにしておけばOK

本田先生の言葉です。
『支援者は基本的に本人の試行錯誤を陰ながら支えていく存在。』
『変な指図しない、横槍入れない、干渉しない。どんな試行錯誤をしているのか、周りの誰かが把握できるか。』
『試行錯誤中は、失敗する。方針転換することがある。いつでも受け入れることができるように、周囲は情報提供ができるような環境は整えておくべきである。』
この試行錯誤を、子どものうちからできていたら…どうでしょうか?
18年間、過干渉に誰かから『こうしなさい、あーしなさい』と生きてきた子どもがいきなり、自分のやりたいことは何か?を考えるのって酷だと思うのです。
今まで誰かの敷いたレールを走ってきた子どもが試行錯誤の仕方がわからないのは当たり前です。
子どもの頃に親から自分の好きなことを認められた子どもはきっと強いと私は信じています。
そして、周囲は、子どもが試行錯誤しやすいように、選択肢を提示していくこと。情報をじゃんじゃん取って、子どもがHelpを出した時に、『こういうのもあるけど、やってみる?』と提示できればそこから子どもは自分に合ったものを選択していくと思います。
その選択肢を拾うために、私達は、医療・福祉・教育などに繋がっておく必要があるでしょう。必ず、1人の子どもを数名で見る体制は取っておいたほうがいいなと思います。(しかし、学校の先生は思いっきり考えが偏っているので、聞き流す程度にした方がいいと個人的には思う)
走り書きで失礼します。
何か感想などありましたら、ぜひゆうまでLINEくださいね♪お話したいです♪
ママはいつでも100点満点!!今日も、頑張りすぎずにいきましょう!!!
今回の記事もよかったな~と思ったら、下のブログ村、ランキングをぽちっと押していただけると嬉しいです♪
この記事を書いている私はこんな人。
小3双子の母。言語聴覚士。
長女は、軽~中等度知的障害、自閉症スペクトラム。ホームスクーラ-。
次女は、軽度のADHD・自閉症スペクトラム。公立小学校の授業を自分で選択し、部分登校している(ハイブリットスクーリング)。
子育て中に、アドラーの心理学を学んだり、教育移住を経験し、『人との対話』が世界で1つの家族の幸せに辿りつける方法だと気付く。 ”置かれた場所で咲きなさい”ではなく、”咲ける場所を探していこう”という子育てスタンスで、学校と学校外の学びの場を重要視している。 子育てをしているママ達が幸せな人生を送り、生き方にフォーカスできるようお茶会・コーチング・コンサル・講座を開催している。『無理』という言葉のない、自分の可能性を無限大に信じられる世界を目指す。
子育て中に、アドラーの心理学と自己理解を一緒に学んでみませんか?
言語聴覚士という専門家だった私が、発達障害児・双子を育ててみて、わかったことは3つ。
1,自分という人間を知れば、子育てがしやすくなる
2,失敗敗を何度も許された人が、人の失敗を許せる
3,自分を律することができるのは、選択肢を持ち選んできた人
私が子育て中に、人が変わったと言われるのは、アドラーの心理学と自己理解があったからと自信を持って言えます。
ぜひ一緒に学んでみませんか??^^
↑クリック。
記事が参考になったと思ったら、押していただけると助かります。
Instagramでは、ブログのまとめをささっと読めます♪
ゆう@発達障がい児×双子ママ (@syuhutago25) on Instagram
Twitterでは、子育て中の気づきを毎日発信しています。
ゆう@発達障がい児×双子ママ (@syuhutago25) on Twitter