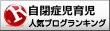こんにちは、ゆうです。
我が長女は現在、地元の区立小学校の支援級に通っています。次女は普通級に通っています。今日は、去年、自分が小学校を見学に行った時に皆さんが質問していた項目や、ここは見た方がいいと思った箇所をお伝えしようと思います。
目次
この記事はこんな方へ向けて書いています。
◆就学相談を受けている方
◆就学前の発達障害や知的障害をお持ちのお子さんの親御さん
この記事を読めばこのような結果が得られます。
◆発達障害や知的障害児の小学校の進路を知ることができる
◆見学する時のポイントがわかる
◆就学相談の流れがわかる
発達障害児、知的障害児の小学校の選択肢

◆通常級・普通級
1クラスの人数は、~35名までと人数が多いです。さまざまな子供と触れ合う機会が持てますが、手厚いサポートは受けられません。
◆特別支援教室(情緒障害等通級指導学級)
都内では、以前まで通級と呼ばれていました。指導員がいない学校には、指導員がいる学校まで訪問しなければならなかったのですが、H29年からは指導員が全ての学校を巡回してくれて、学校をまたぐことなく在籍校で指導が受けられる『特別支援教室』という 形に変更されました。助かりますね。
週に数時間、普通級の教室から特別支援教室に行って学習します。ですので、基本的にその数時間の勉強を補える子なので、障害の程度が軽い子向けです。
特別支援教室に通う子の例)
他人とのコミュニケーションが苦手
落ち着きがない
言葉が遅れている
興味が偏っているなど
◆特別支援学級
少人数で、個別に支援計画を立ててくれる学級をいいます。地域によっては知的、情緒と別れている所もあります。(難聴などは割愛します)
支援学校とは違い、『先生が特別支援の教員免許を持っているかわからない』という点があります。(私の区の支援学級の先生は皆さん持っているとの回答でした)
登下校は、この学級に所属しているうちは送り迎えが必須です。(高学年になり、1人で通学できる子もいるそう。)
支援学校か学級で迷う時に、どうしたらよいか…現役の小児STに伺った所
『トイレが自立』
『言葉が出ている』
『着替えがある程度自立している』
『椅子に20分~30分程度座れる』
などをクリアしていると、支援学級でいけるのではないかという回答をもらいました。
◆特別支援学校
少人数制で、支援学校の先生は通常の教育免許特別支援学校の教員免許を持っています。
上記の項目がクリアできていない知的障害重度~中等度、発達障害の重いお子さんがこちらに該当するかと思います。
支援級同様、個別に『特別支援計画』立てていただけます。
登下校は、送迎バス通学か送り迎えです。
小学校の学区問題

私の区では、越境(学区を超える)が許されません。また、区をまたいで支援級を希望することもできません。もしも、区をまたいで希望する場合は、その学校に兄弟がいるか・住所や勤務地がそこにあるか…をクリアしないといけません。
学区問題の裏事情
うちの区だけかわかりませんが…、人数がかなり少なくて、PTAや学校が『ぜひ、我が校に来てほしい』と切望していれば、その学区内で幽霊勤務(その区で勤務しているという住所だけくれる。実際には働かない。)させてくれる職場を紹介してもらえるそうです。
小学校を支援級見学する時のポイント

①校長の雰囲気、考え方
なんと言おうと、校長が全ての権限を持っています。話しやすそうな人か、考え方は自分と合うかなどを見てみましょう。
②在校生の雰囲気、男女比、クラス構成
1~5年生の雰囲気は我が子と合いそうか?
男女比はどうか?
もしも、クラスがあるのならば、学年で分けているのか?学年関係なくわけているのか?障害のタイプでわけているのか?
③授業や宿題の進め方
プリントや教材は何を使用しているか?
タブレット端末などの使用をしているか?
宿題はどの程度出るのか?
④教員、支援員の配置、雰囲気、知識など
特別支援の教員免許を持っているか?(聞きにくかったら、役所の人に聞いてみましょう)
支援員は、毎日ついてくれるのか?
授業中の声掛け方法
(しかし、先生は異動があるのであまり重視しない)
⑤環境
黒板や掲示物などは構造化されているか?(わかりやすいか)
逆に、刺激になりすぎてないか?
クールダウン時は別室か?パーテーションで区切るか?
トイレ(和か洋か)の場所の確認
⑥普通級との交流
現在、コロナの影響で、我が校では交流級がありません。
⑦小学校後の進路
卒業生はどこの中学校へ進学しているか?
⑧PTAの参加率
行事はどのように参加するか?
PTAはどの程度参加するのか?(我が学級ではPTAの仕事は免除されます)
⑨民間や公的な保育所等訪問支援が使えるか?
幼稚園や保育園で利用していた保育所等訪問支援が利用できるかどうかを聞いてみましょう。ちなみに、我が学校では、部外者をなるべく入れないという方針なのか使えませんでした…(ショック)。その代わり、スクールカウンセラーと早めに繋がり、授業の様子を見てもらいました。
保育所等訪問支援についてはこちら↓↓↓
就学相談の流れ
去年の私のスケジュールを公開します。*地域によってスケジュールは異なります。
7月 申し込み
7月 役所の担当者と面談
9月 田中ビネー検査、行動観察、ドクター面談
10月 見学・体験
11月 就学先決定
12月 就学支援シートを記入して幼稚園、療育センターに記入してもらう
3月 就学支援シート小学校へ提出
*ポイント
担当者の面談や見学は、できるだけ父母でいきましょう。夫婦間での意見の相違があるとややこしいことになるので、一緒に面談を受けた方がいいでしょう。
学校見学は校長先生とお話できるチャンスだと思います。
発達障害児、知的障害児の小学校選びは、悩んで悩んで悩んで…。
私の場合、悩みに悩んで、胃がキリキリするほどでした。しかし、悩みすぎた後にこう思ったんです。『とりあえず入ってみて、合わないって思ったら、すぐ変えればいい。ホームスクールも覚悟する。先生と蜜にコミュニケーションを取れればそれでいい。すぐにスクールカウンセラーに相談する!』と覚悟して、決定しました。
6月から勉強が始まり、次女が勉強にあまりついていけなくなってしましました…。ですので、今現在、支援級に移籍できるように役所に働きかけています。スクールカウンセラーと担任とは連携がうまくいっており、両者からは了承を得られています。入ってみないとわからない事も沢山あります。それから変更も可能なので…あまり悩みすぎず…と言っても、悩むとは思いますが、悩んで悩んで悩んで出たあなたの決定は間違っていないと思います。
まとめ
発達障害の就学の選択肢、学区問題、見学のポイント、就学相談の流れをお伝えしました。去年の今頃から、悩んでいたなぁ…懐かしいです…。今も、問題は山積みですが…悩んでいる間にも、子ども達は少しずつ成長しています。成長を見逃さないように、子供をしっかり見ていきましょう!
今日もお付き合いありがとうございました。
↑クリック。
記事が参考になったと思ったら、押していただけると助かります。
子育て中に、アドラーの心理学と自己理解を一緒に学んでみませんか?
言語聴覚士という専門家だった私が、発達障害児・双子を育ててみて、わかったことは3つ。
1,自分という人間を知れば、子育てがしやすくなる
2,失敗敗を何度も許された人が、人の失敗を許せる
3,自分を律することができるのは、選択肢を持ち選んできた人
私が子育て中に、人が変わったと言われるのは、アドラーの心理学と自己理解があったからと自信を持って言えます。
ぜひ一緒に学んでみませんか??^^